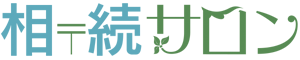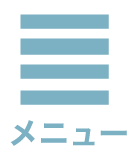【遺留分】
遺言などがある場合でも、相続人のうち一定のものは必ず一定の割合の相続分を確保できる制度があります。この割合の財産は「遺留分」といい、遺留分を有する相続人を「遺留分権利者」といいます。 この遺留分権利者の範囲は、配偶者と子、直系尊属のみとなっており、兄弟姉妹に遺留分はありません。
【分割協議後の遺留分減殺請求】
生前贈与、遺言がなく、遺産分割協議が行われた場合には、遺留分という概念が存在しないことになります。また、生前贈与、遺言があった場合でも、遺産分割協議で決定した財産に対しては、遺留分減殺請求はできません。
【遺留分】
遺言などがある場合でも、相続人のうち一定のものは必ず一定の割合の相続分を確保できる制度があります。この割合の財産は「遺留分」といい、遺留分を有する相続人を「遺留分権利者」といいます。 この遺留分権利者の範囲は、配偶者と子(代襲相続人も含む)、直系尊属のみとなっており、兄弟姉妹には遺留分はありません。
※遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
①相続人が直系尊属(父母など)のみの場合 遺留分の算定基礎となる金額の1/3
②上記以外(配偶者や子を含む)場合 遺留分の算定基礎となる金額の1/2
【兄弟姉妹の遺留分】
被相続人の兄弟姉妹は、それぞれ独立に生計を立てていると考えられ、被相続人の財産形成に貢献したとは考えにくいため遺留分は認められていません。
【相続開始前の遺留分の放棄】
相続開始前における遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を必要とします。相当の撤回理由がない限り撤回はできません。
【遺留分を侵害する内容の遺言】
遺留分を有する相続人は、遺留分減殺請求権を行使することができますが、遺言自体が無効になるわけではありません。
【遺留分放棄】
遺留分権利者が、相続開始後に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可を受ける必要はありません。なお、被相続人の生前に遺留分の放棄をする場合には、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。
【代償性のある遺留分放棄】
遺留分の放棄は、代償性がある(特別受益があるか、放棄と引き換えに現金を貰う等)場合でも、本人の意思に基づかなくては、家庭裁判所の許可を受けることができません。
【兄弟の遺留分の請求】
兄弟には遺留分は認められていませんので、遺言通り長兄が相続することになります。
【遺留分算定基礎財産の評価額】
遺留分算定基礎財産に算入する価額は、原則として、相続開始時点の評価額によります。ただし、「遺留分に関する民法の特例」により、自社株式等を固定合意の対象とすれば、遺留分算定基礎財産の価額を合意時点の評価額とすることができます。
①必ず遺言書を作成すること。
②遺言書に遺言執行者を指定しておくこと。
③相続発生の順番によっては遺留分の割合に変動が生じる。
【遺留分の放棄と遺言】
遺言がないと、遺留分の放棄は相続の放棄ではないので、遺産分割協議が必要となり、遺留分を放棄した相続人も共同相続人の一人となります。
【遺留分】
遺言などがある場合でも、相続人のうち一定のものは必ず一定の割合の相続分を確保できる制度があります。この割合の財産は「遺留分」といい、遺留分を有する相続人を「遺留分権利者」といいます。この遺留分権利者の範囲は、配偶者と子、直系尊属のみとなっており、兄弟姉妹に遺留分はありません。
※遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
①相続人が直系尊属(父母など)のみの場合 遺留分の算定基礎となる金額の1/3
②上記以外(配偶者や子を含む)場合 遺留分の算定基礎となる金額の1/2
【遺留分の放棄】
遺留分の生前放棄は認められています。
遺留分の生前放棄は、家庭裁判所へ遺留分放棄許可審判申立を行い家庭裁判所の許可を受けなければなりません。
【遺留分算定の基礎となる財産】
遺留分算定の基礎となる財産は、原則として、被相続人が相続開始の際に有した財産の価額に生前贈与財産の価額(原則として、相続開始時点の評価額)を加え、債務の全額を控除して算定します。
生前贈与財産の価額は、原則として、相続開始時点の評価額です。なお、遺留分算定の基礎となる財産に加える贈与財産は、原則として、相続開始前1年以内に贈与されたものが対象となりますが、遺留分を害することを被相続人および受贈者が知ってなされたものについては、1年より前の贈与財産も含まれます。また、相続人の特別受益分は年限がなく持ち戻しとなります。
【配偶者と兄弟姉妹の遺留分】
兄弟姉妹には遺留分がないのでゼロになり、配偶者の遺留分は財産の2分の1となります。
【遺留分放棄と代襲相続】
代襲者(質問者)は被代襲者(父)の有した権利のみを取得できるにすぎないと考えられるため、この場合被代襲者(父)が遺留分を放棄しているので、あなたは、それを必然的に引き継ぐことになり、遺留分はなく、よって減殺請求もできないということになります。
【遺留分減殺請求の行使】
遺留分減殺請求権は、必ずしも訴えの方法によることを要せず、相手方に対する意思表示によってなせば足りますが、後日の争いをできる限り回避し、事後の立証の便宜のため配達証明付内容証明郵便により行うとよいでしょう。
遺留分減殺請求権には時効があります。
【遺留分減殺請求権の時効】
遺留分減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、 遺留分減殺請求をしうることを知ったときから1年以内に行使しなければ時効で消滅します。
また、これらの事実を知らなくとも、相続の開始から単に10年が経過した場合も同様に権利行使できなくなります。
【生前贈与財産と遺留分減殺請求】
被相続人が相続人以外(相続人を含む)に生前贈与した財産がある場合、生前贈与された財産は、被相続人の相続開始前1年以内に贈与されたもののみ、遺留分減殺請求の対象となるのが原則です。
【生前贈与財産と遺留分減殺請求】
受贈者が相続人であり、当該贈与が特別受益にあたる場合には、贈与された財産は原則として遺留分減殺請求の対象なります。
【遺留分減殺請求の時効】
遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないとき、また相続の開始のときから10年を経過した場合には消滅します。
【遺留分減殺請求により遺留分を超える額の資産の取得があった場合】
遺留分迄の部分は相続で、遺留分を超える部分は贈与で取得したことになり、贈与部分には贈与税が発生します。
【遺贈と贈与がある場合の遺留分減殺請求】
遺贈を減殺した後でなければ贈与を減殺することができません。
【複数ある遺贈から遺留分減殺請求をする】
遺贈間での先後関係はなく、全部の遺贈がその価額の割合に応じて減殺されることとなります。遺言者が遺言で別段の規定をしているときは、それに従います。
【複数ある贈与から遺留分減殺請求をする】
新しい贈与から減殺し、順に前の (過去の) 贈与に及ぶことになります。新旧の判断は、登記や登録の日時でなく契約の日時によって行われることとされています。
【遺留分減殺請求の行使前に第三者に譲渡された場合】
遺留分権利者は、第三者に遺留分減殺を主張することはできず、受贈者に対して価額の弁償を請求できるにすぎません。ただし、第三者が譲渡当時、遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には、第三者に対しても現物の返還を請求することができます。この場合、第三者は価額を返還して現物の返還を免れることができます。
【遺留分減殺請求権と債権者代位権】
債権者代位権とは、債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる(債権者代位権:民法423条1項本文)権利です。ただし、債務者の一身に専属する権利は、代位行使することができない(民法423条但書)とされています。
債務者が有する遺留分減殺請求権も債権者代位権の対象となるかが問題となりますが、遺留分減殺請求権も、これを行使するか否かが遺留分権利者の意思に委ねられているため、423条1項但書にいう一身専属権です。よって、遺留分減殺請求権を第三者に譲渡するなど、遺留分権利者たる債務者が、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位権の目的とすることはできません(最判平13・11・22)。
【遺留分減殺請求権の行使の方法】
遺留分減殺請求権の行使は、受遺者又は受贈者に対する意思表示によってすれば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、いったんその意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生じます。
【遺留分減殺請求の意思表示】
遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれるとされます(最判平10・ 6 ・11)。
《相続人の一部の者に遺贈された場合》
遺留分減殺請求権は、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合にも認められます。
【共同相続人内における寄与者に対する遺留分減殺請求】
他の相続人が遺留分減殺請求をすることはできないとされています。
理由としては、遺留分算定の基礎財産 (相続債務を控除) と寄与分算定の基礎財産 (相続債務は非控除) とが異なるものであり、遺留分減殺請求権は通常の訴訟によって行使される権利であるのに対し、寄与分は家庭裁判所の調停、審判により決定される権利であること、寄与分をもって遺留分減殺請求に対抗することが法技術的に困難といえるためとされています。
【共同相続人内における寄与者に対する遺留分減殺請求】
遺留分を侵害された共同相続人は、遺贈について減殺請求をすることができます。寄与分は、共同相続人の協議において定め、協議が整わないときは寄与者の請求により、家庭裁判所における調停・審判によって定める(904条の2の②)とされています。
これ以外の方法、例えば遺言によって寄与分を定めても法的な強制力はありません。
したがって、寄与者に対して、、相続分の指定や遺贈あるいは「相続させる」遺言によって法定相続分以上の財産を帰属させる意思表示をした場合、それらが遺留分を侵害する場合は、寄与分との関係は問題にならず、遺贈等は減殺請求の対象になります。
【遺贈と寄与分】
904条の2第3項から寄与分は被相続人が相続開始時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることが出来ませんので、遺贈された財産に寄与分は認められず、全財産が遺贈されると寄与分が成立する余地が無くなります。